Multiple aquatic invasions by an endemic, terrestrial Hawaiian moth radiation
Rubinoff & Schmitz 2010 PNAS
水中と陸上で同様に生活できるガの仲間の系統と進化に関する論文。
水中と陸上とで同様に生活できる昆虫の存在は従来知られていませんでした。しかし、この論文で紹介されている、ハワイのみに存在するHyposmocomaと呼ばれるガのグループは、水中でも陸上でも同様に活動でき、水中で蛹になることもできるということです。
DNAを使った系統解析の結果から、Hyposmocoma属の中の、特徴的な殻の形をもつ 3つのグループはそれぞれ単系統であること、そして、水中への適応はそれぞれのグループで独立に獲得されたことがわかりました。このような「水陸両用」な生活形態が複数回独立に獲得されたことを示す例は他には存在しないとのことです。
このような特殊な適応が複数の近縁の系統に何度も表れる現象はハワイのほかの生物にも見られるようです。筆者らは、そのような現象とハワイが他の地域から隔絶されていることとの関連性を指摘しています。ハワイには大陸の水系に存在する多くの水生昆虫が存在しないため、水中への適応が進化する機会が多く存在した可能性がある、と述べられています。
また、筆者らは、このガのグループはほとんどが特定の火山にある渓流近くにのみ生息し、開発などによって減少が心配される、もしくはすでに絶滅した可能性がある、とも指摘し、先手をとっての環境保護の重要性に触れています。
--
この論文は新聞で紹介されていたのを見て知りました。
「水陸両用」のガの幼虫、米科学者が発見 -YOMIURI ONLINE
「水陸両用」なのも驚きですが、見た目がトビケラに良く似ているのも驚きです。特徴的な形をした殻を作ることや、絹糸を使って体を固定するといった、水中への適応も同じです。
論文を読んだ限りではハワイにはトビケラはいないようです。トビケラと近縁のガの仲間が同様の形質を進化させて、本来トビケラが入っているニッチに入っている(入りつつある?)、というのは、進化の予測可能性とか、以前紹介した論文にもあったPhylogenetic conservatismとかに関係があるような気がします。
(論文の内容はPNASにアクセスできないと見れませんが、Supporting Informationの動画は見ることができるようです)
2010年3月31日水曜日
2010年3月30日火曜日
ノートを探して
新しいノートを探しています。
以前使っていた大学のロゴの入ったものが、たった1年で見る影もなくボロボロになってしまったので、新しいものを買うことにしました。前のものは紙のハードカバーのものでしたが、こんどはより頑丈なものにしようと考えました。
しかしいざ探してみるとこれといったものがなかなか見つかりません。
大学の先生たちは、どこから手に入れてくるのか、シンプルで頑丈そうなハードカバーのノートを持っているんですが、そういったものが見つかりません。大学の生協(に相当する店)には以前使っていたもの以外には1種類だけしかありませんでした。
他の文房具店を巡ってみても、あまり収穫がなかったので、結局生協のものを買うことにしました。イギリスではわりとメジャーなBlack n' Redというブランドのものです。
しかし、このブランドのノートはあまり好きではありません。
まず第一に重過ぎるし、地下鉄の路線図とか不要なものがついていて気に障ります。”サヴィル・ロウのスーツをもらおう”みたいなキャンペーンもブランドイメージ作りに必死な感じがして、微妙な感じです。さらにこのノートはとある有名研究者も使っていると知って、さらにやる気が減少しました。(別にその有名研究者が嫌いなわけではありません。ただ有名人と同じということが嫌なだけです)
なにより腹が立つのは、そのくせ、やけに頑丈で、なおかつ書きやすいことです。頑丈なノートを探しているので、このノートは最適かもしれません。
嫌いな人が優秀だったときに感じるやるせない感情をノートに感じることになるとは。
結局、いまのところこれ以外に選択肢はなさそうなのでとりあえず、black n' redを使うことにしましたが、他の選択肢がないか引き続き探索中です。
以前使っていた大学のロゴの入ったものが、たった1年で見る影もなくボロボロになってしまったので、新しいものを買うことにしました。前のものは紙のハードカバーのものでしたが、こんどはより頑丈なものにしようと考えました。
しかしいざ探してみるとこれといったものがなかなか見つかりません。
大学の先生たちは、どこから手に入れてくるのか、シンプルで頑丈そうなハードカバーのノートを持っているんですが、そういったものが見つかりません。大学の生協(に相当する店)には以前使っていたもの以外には1種類だけしかありませんでした。
他の文房具店を巡ってみても、あまり収穫がなかったので、結局生協のものを買うことにしました。イギリスではわりとメジャーなBlack n' Redというブランドのものです。
しかし、このブランドのノートはあまり好きではありません。
まず第一に重過ぎるし、地下鉄の路線図とか不要なものがついていて気に障ります。”サヴィル・ロウのスーツをもらおう”みたいなキャンペーンもブランドイメージ作りに必死な感じがして、微妙な感じです。さらにこのノートはとある有名研究者も使っていると知って、さらにやる気が減少しました。(別にその有名研究者が嫌いなわけではありません。ただ有名人と同じということが嫌なだけです)
なにより腹が立つのは、そのくせ、やけに頑丈で、なおかつ書きやすいことです。頑丈なノートを探しているので、このノートは最適かもしれません。
嫌いな人が優秀だったときに感じるやるせない感情をノートに感じることになるとは。
結局、いまのところこれ以外に選択肢はなさそうなのでとりあえず、black n' redを使うことにしましたが、他の選択肢がないか引き続き探索中です。
2010年3月23日火曜日
[本]The Oxford Book of Modern Science Writing - 科学者の展覧会
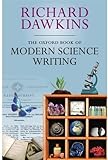 The Oxford Book of Modern Science Writing
The Oxford Book of Modern Science WritingRichard Dawkins
リチャード・ドーキンスによる、科学者が書いた文章のアンソロジー。邦訳はまだされていないようです。
本の内容は20世紀の著名な科学者が書いた本や論文からの抜粋に、ドーキンスが短い紹介文を付けたものを集めたものです。
取り上げられている科学者は、アインシュタインやホーキングといった世界的に有名な物理学者から、フィッシャーやマイアといった20世紀前半の進化生物学者、DNAで有名なワトソンとクリックなどの分子生物学者、それに加えて古生物学者や数学者などです。20世紀の科学の発展の様子がよく理解できる、多様で幅広い選択です。
実は正直に言うとこの本、読む前はそれほど内容には期待していませんでした。いくらリチャード・ドーキンスが編集したとはいえ、本や論文の一部分を取り上げただけで、それぞれの科学者の偉業が理解できるはずがない、と敬遠していました。
しかし、実際に読んでみると、とても面白かったです。
まるで、美術館でたくさんの画家の絵を順番に観るように、次々に個性的な科学者の文章が現れます。数ページの文章だけで科学者1人1人の全てを理解することは到底できませんが、多くの文章をざっと見ることで科学者たちの個性やアイデアの多様さを感じることができます。
また、印象に残った科学者の文章の原著を実際に読んでみる、という科学書の世界へのプライマーとしても良くできています。(ドーキンス自身がそれがこの本の役割であると述べています)
個人的な好みを言うと、やはり生物学者の文章が気に入りました。例えば、レイチェル・カーソンの英文はこの本で初めて読みましたが、とても綺麗で、カーソンが環境保護のリーダー足りえたのはその文才によるところもあるのかな、と感じました。ほかにも、分子生物学者シドニー・ブレナーの新千年紀にむけた新しい生物学の方向性を説いた文章は、普通の一般向け科学書には取り上げられそうにないですが、内容がとても示唆に富んでいると思います。
ちょっとした枕になりそうな大きさの本ですが、1つ1つの抜粋は短いので、暇な時に少しずつ読みするめることもできます。そんなところも良い点だと思います。
2010年3月20日土曜日
マグロについて日本政府に望むこと-2
1つ前のエントリーではこちらのニュースにあるクロマグロの禁輸案の背景についてまとめました。このエントリーでは、日本政府が根本的な問題解決のためにできると思うことを書いてみます。
今回問題になった禁輸案のような対立はあらゆる漁業資源におこりうることです。それらの対立を解消する最も自然な方法は、日本の政府自身が持続可能な漁業の実現に積極的にとりくむことだと思います。
以下に日本政府に期待する積極的な取り組みかたのポイントを挙げてみます。
1.持続可能な漁業に対する取り組みでリーダーシップを発揮する
上の読売新聞の記事で赤松農林水産大臣は以下のように述べています。
日本人はこのような提案を理不尽な外圧と捉える必要はないと思います。
知ってのとおり日本には多様な魚介類の食文化が存在します。多様な食文化は海の生物多様性の反映であり、日本人の誰も乱獲によってその多様性が失われることを望んではいないはずです。
ゆえに、日本の政府は、"日本人の食文化は海の生物多様性によって支えられている、ゆえにどの国よりも率先して資源の管理に参加する"という態度を表明するべきだと考えます。
(これは、日本人の食文化に対する思いをヨーロッパの人々に理解できる言葉に訳して伝えると言い換えることができるかもしれません。)
まず、赤松農相がいうように日本が厳密な資源管理を行ってきたのなら、そのことを積極的に伝えることです。(伝える方法は"科学的"に。これは2.で書きます)
また、今回の提案の原因になったクロマグロの減少は、輸出のための乱獲が原因の1つだと言われています。直接の漁獲量だけでなく、輸出入に際して、持続可能な漁が行われているかどうかの追跡を可能にするルール作りにも参加する必要もあります。
2.科学的な方法で成果を伝える
上にあげた取り組みの結果は"科学的に"世界に発信していくべきだと思います。
これは、日本が現在行っている調査捕鯨のような、別の意味で『科学的』な方法ではなく、通常の科学の方法で成果を発信することを意味しています。
国の機関が調査の結果を伝えるという形式ではなく、第三者である研究機関や大学の研究者の手で、資源管理の有効性を調べ、学術論文として発表する、という形をとるのが最もわかりやすく、説得力があり、かつ透明性のある方法だと思います。
日本の政府や漁業者の取り組みは海外のメディアには常に伝わりにくく、欧米の運動家や政治家の英語以外で書かれた情報に対する感度は低いものです。また政府関連機関の発表は日本のものに限らず疑いの目で見られがちです。
学術論文は最も説得力のある日本人の取り組みの証拠として受け入れられるはずです。加えて、科学的な情報発信は、日本の科学者が常日ごろ行っていることなので、政治的な駆け引きをするよりも簡単でかつ安全です。
+α.ルール作りはユニバーサルな方法で
日本政府がリーダーシップをとるときに気をつけるべきことは、"日本独自の手法"にこだわらないことだと思います。以下のblogエントリに書いてあることは日本人が国際社会でリーダーシップをとるときに常に気に留めておくことだと思います。
日本色の付いた技術ではもう世界で勝てない -フランスの日々
以上です。
これまで、日本政府、そしてなにより日本のメディアは、水産資源に関する欧米諸国との対立を、政治的あるいは文化的な対立として国民に伝えてきました。今回の禁輸案の否決に関しても政治的駆け引きの成功を伝えるニュースがメディアによって伝えられています。
このような姿勢が原因か、ヨーロッパ諸国に対する反感を表す意見もネット上で見られます。
生物資源の利用を考えるとき、"獲りすぎた結果、獲れなくなることを望む人はいない"という最も基本的で、全ての文化に共通する前提を決して忘れることがないようにして欲しいと思います。
今回問題になった禁輸案のような対立はあらゆる漁業資源におこりうることです。それらの対立を解消する最も自然な方法は、日本の政府自身が持続可能な漁業の実現に積極的にとりくむことだと思います。
以下に日本政府に期待する積極的な取り組みかたのポイントを挙げてみます。
1.持続可能な漁業に対する取り組みでリーダーシップを発揮する
上の読売新聞の記事で赤松農林水産大臣は以下のように述べています。
"資源管理については日本の積極的な姿勢を各国に訴えてきた。我々が想像した以上の良い結果が出た"そして、次のようにも述べています。
"太平洋、インド洋などでも資源管理、調査を行い、日本がリーダーシップを取っていくことが大事だ"近年のヨーロッパでは"持続可能でない自然の利用は一切認めない"という方向に社会が動いています。スーパーの魚売り場に行けば必ず"Sustainably sourced ○○"と持続可能性に関する記述が見られます(たとえばこのようなマークがついている)。だから、今回のEU諸国の提案は現在の流れを考えると当然のものとも考えられます。
日本人はこのような提案を理不尽な外圧と捉える必要はないと思います。
知ってのとおり日本には多様な魚介類の食文化が存在します。多様な食文化は海の生物多様性の反映であり、日本人の誰も乱獲によってその多様性が失われることを望んではいないはずです。
ゆえに、日本の政府は、"日本人の食文化は海の生物多様性によって支えられている、ゆえにどの国よりも率先して資源の管理に参加する"という態度を表明するべきだと考えます。
(これは、日本人の食文化に対する思いをヨーロッパの人々に理解できる言葉に訳して伝えると言い換えることができるかもしれません。)
まず、赤松農相がいうように日本が厳密な資源管理を行ってきたのなら、そのことを積極的に伝えることです。(伝える方法は"科学的"に。これは2.で書きます)
また、今回の提案の原因になったクロマグロの減少は、輸出のための乱獲が原因の1つだと言われています。直接の漁獲量だけでなく、輸出入に際して、持続可能な漁が行われているかどうかの追跡を可能にするルール作りにも参加する必要もあります。
2.科学的な方法で成果を伝える
上にあげた取り組みの結果は"科学的に"世界に発信していくべきだと思います。
これは、日本が現在行っている調査捕鯨のような、別の意味で『科学的』な方法ではなく、通常の科学の方法で成果を発信することを意味しています。
国の機関が調査の結果を伝えるという形式ではなく、第三者である研究機関や大学の研究者の手で、資源管理の有効性を調べ、学術論文として発表する、という形をとるのが最もわかりやすく、説得力があり、かつ透明性のある方法だと思います。
日本の政府や漁業者の取り組みは海外のメディアには常に伝わりにくく、欧米の運動家や政治家の英語以外で書かれた情報に対する感度は低いものです。また政府関連機関の発表は日本のものに限らず疑いの目で見られがちです。
学術論文は最も説得力のある日本人の取り組みの証拠として受け入れられるはずです。加えて、科学的な情報発信は、日本の科学者が常日ごろ行っていることなので、政治的な駆け引きをするよりも簡単でかつ安全です。
+α.ルール作りはユニバーサルな方法で
日本政府がリーダーシップをとるときに気をつけるべきことは、"日本独自の手法"にこだわらないことだと思います。以下のblogエントリに書いてあることは日本人が国際社会でリーダーシップをとるときに常に気に留めておくことだと思います。
日本色の付いた技術ではもう世界で勝てない -フランスの日々
以上です。
これまで、日本政府、そしてなにより日本のメディアは、水産資源に関する欧米諸国との対立を、政治的あるいは文化的な対立として国民に伝えてきました。今回の禁輸案の否決に関しても政治的駆け引きの成功を伝えるニュースがメディアによって伝えられています。
このような姿勢が原因か、ヨーロッパ諸国に対する反感を表す意見もネット上で見られます。
生物資源の利用を考えるとき、"獲りすぎた結果、獲れなくなることを望む人はいない"という最も基本的で、全ての文化に共通する前提を決して忘れることがないようにして欲しいと思います。
マグロについて日本政府に望むこと-1
ここ数日日本のメディアを騒がせていたクロマグロの禁輸に関する問題は、一応の決着がついたようです。
大西洋・地中海産クロマグロ禁輸案を否決 -YOMIURI ONLINE
日本の水産や流通関係者はとりあえず胸をなでおろした、といったところでしょうか。
しかし、大西洋においてクロマグロが減少していることが事実であるならば、同様の提案は遅かれ早かれまた行われると思われます。その度に、政治的駆け引きで乗り切るのもよいですが、日本政府はそろそろ根本的な問題の解決を目指していくべきだと思います。
そこで問題解決に際して日本政府に期待することを少し書いてみたいと思います。
僕は保全生物学の専門家ではないですし、国際機関の舞台裏を知っているわけでもありません。ここではインターネットを介して得られる情報と生物学を学ぶ学生としての常識的判断に基づいて書いていくことにします。
まず、問題の背景から始めます。
今回のワシントン条約の締約国会議で大西洋クロマグロ(以下クロマグロ)の禁輸が提案された直接の理由は、去年11月の「大西洋まぐろ類保存国際委員会」(以下ICCAT)の会合で決定されたクロマグロの漁獲枠における対立にあるそうです。かねてから減少が指摘されていたクロマグロの絶滅を防ぐにはICCATの漁獲枠は大きすぎる、とEU内のいくつかの国が主張しました。それらの国は絶滅危惧動物の保護を目的とするワシントン条約においてクロマグロを絶滅危惧種として扱うことによって取引を大幅に規制し、それによって保護を進めようと試みました。
クロマグロの最大の輸入国である日本にとって、この取引の規制が実現することは大きな問題でした。(WWFのウェブサイトによると世界で消費されるクロマグロの80%を日本が消費しているとのことです)
クロマグロの輸入が行えなくなると、外食産業、輸入業者などが受ける打撃は大きく、日本としてはこの提案をできれば否決したい、との考えの下、多くの交渉活動を行ったようです。
結果、今回提出された、モナコによる案、EUによる案がともに反対多数で否決されたとのことです。提案が否決された背景には日本の活動だけでなく、反欧米主義やEU圏内での対立もあったようです。
このような形で今回の提案は否決されましたが、調査によるとクロマグロの量は乱獲が行われないときと比較して15%にまで減少しており、加えて、ICCATの科学者の提唱する持続可能な漁獲量は会議に参加した国には受け入れられなかったそうです。(こちらもWWFより)
日本によるクロマグロの輸入量は年々増加しています。一方でヨーロッパにおいては持続可能な漁業は"常識"になりつつあります。
このままクロマグロの乱獲が続き、資源量が減少するなら、漁業の持続可能性を重要視するEU諸国から将来同様の提案が持ち出される可能性があることは想像に難くないと思います。
そこで日本政府にはこのような提案に対して場当たり的な政治的対応をするだけでなく、問題の根本的な解決を進めて行くこと、すなわち持続可能な漁業の推進により積極的に関わっていくこと、を期待したいと思います。
もう少し具体的な内容は次のエントリで。
大西洋・地中海産クロマグロ禁輸案を否決 -YOMIURI ONLINE
日本の水産や流通関係者はとりあえず胸をなでおろした、といったところでしょうか。
しかし、大西洋においてクロマグロが減少していることが事実であるならば、同様の提案は遅かれ早かれまた行われると思われます。その度に、政治的駆け引きで乗り切るのもよいですが、日本政府はそろそろ根本的な問題の解決を目指していくべきだと思います。
そこで問題解決に際して日本政府に期待することを少し書いてみたいと思います。
僕は保全生物学の専門家ではないですし、国際機関の舞台裏を知っているわけでもありません。ここではインターネットを介して得られる情報と生物学を学ぶ学生としての常識的判断に基づいて書いていくことにします。
まず、問題の背景から始めます。
今回のワシントン条約の締約国会議で大西洋クロマグロ(以下クロマグロ)の禁輸が提案された直接の理由は、去年11月の「大西洋まぐろ類保存国際委員会」(以下ICCAT)の会合で決定されたクロマグロの漁獲枠における対立にあるそうです。かねてから減少が指摘されていたクロマグロの絶滅を防ぐにはICCATの漁獲枠は大きすぎる、とEU内のいくつかの国が主張しました。それらの国は絶滅危惧動物の保護を目的とするワシントン条約においてクロマグロを絶滅危惧種として扱うことによって取引を大幅に規制し、それによって保護を進めようと試みました。
クロマグロの最大の輸入国である日本にとって、この取引の規制が実現することは大きな問題でした。(WWFのウェブサイトによると世界で消費されるクロマグロの80%を日本が消費しているとのことです)
クロマグロの輸入が行えなくなると、外食産業、輸入業者などが受ける打撃は大きく、日本としてはこの提案をできれば否決したい、との考えの下、多くの交渉活動を行ったようです。
結果、今回提出された、モナコによる案、EUによる案がともに反対多数で否決されたとのことです。提案が否決された背景には日本の活動だけでなく、反欧米主義やEU圏内での対立もあったようです。
このような形で今回の提案は否決されましたが、調査によるとクロマグロの量は乱獲が行われないときと比較して15%にまで減少しており、加えて、ICCATの科学者の提唱する持続可能な漁獲量は会議に参加した国には受け入れられなかったそうです。(こちらもWWFより)
日本によるクロマグロの輸入量は年々増加しています。一方でヨーロッパにおいては持続可能な漁業は"常識"になりつつあります。
このままクロマグロの乱獲が続き、資源量が減少するなら、漁業の持続可能性を重要視するEU諸国から将来同様の提案が持ち出される可能性があることは想像に難くないと思います。
そこで日本政府にはこのような提案に対して場当たり的な政治的対応をするだけでなく、問題の根本的な解決を進めて行くこと、すなわち持続可能な漁業の推進により積極的に関わっていくこと、を期待したいと思います。
もう少し具体的な内容は次のエントリで。
2010年3月15日月曜日
種分化の原動力-2
先日のエントリではこちらの論文を紹介しました。
この論文はそのセンセーショナルな内容のためか、さまざまな場所で取り上げられたようです。
先週のNew Scientistの表紙を飾った記事、
Accidental origins: Where species come from -New Scientist
やNature Podcastのインタビュー、大学でのジャーナルクラブ(論文の輪読会のようなもの)のお題になったり、日本のブログでも取り上げている記事がありました。
赤の女王仮説 -サイエンスあれこれ
比較的良く知られているように、ダーウィンは著書『種の起源』の中で種分化の原因を必ずしも明確に説明していません。ダーウィンは自然選択によって適応的な進化がおこることを明確に示しました。しかし種分化については異なる適応の結果、異なるタイプの生き物のグループ、すなわち新しい種、が生まれるのは自明であるようにあつかっていたと記憶しています。(うろおぼえですが)
しかし、この論文の結果は自然選択は種分化の主原因ではない可能性を示しています。
論文内の印象的な部分を引用してみると、
この考え方は、"種分化は適応的な変化によって徐々に引き起こされる"という従来の考え方に反しています。その点がメディアなどで取り上げられた理由だと思います。
しかしこの結果には納得のいく部分が多くあります。
まず自然のなかで実際に観察される種分化の痕跡は、ほとんどが稀なイベントの結果と考えられているからです。たとえば、地理的な隔離や離島への稀な移住のイベント、染色体数の変化などはすべてこれらに当てはまります。それに加えて生物の移動能力(稀なイベントの起こりやすさと考えられる)が種分化の頻度と関係があることも知られています。
ガラパゴス諸島のフィンチのように明らかに自然選択による適応の結果、種が分化したように見える例も存在します。しかし、このような明確な例はそれほど多くみつかっていません。(それを支持するとされる間接的な観察結果は多くあると思いますが。)
また、ショウジョウバエなどをつかった種分化と自然選択に関する研究も、選択を受けるハエのグループ間はすでに隔離されていることが前提になっています。
自然界において"自然選択の結果徐々におこる種分化"があまり観察されないのは、そもそもそれがあまり起こっていないからかもしれないというのは筋が通った考えだと思います。
しかし同時に種分化のプロセスが完全にランダム性のみに支配されているというのも、少し居心地の悪い気がします。
上のNew Sceintistの記事の中のDaniel Raboskyの指摘は的を得ていると思います。
いずれにせよ、筆者らがいう"稀なイベントのカタログのサイズを知ること"は種分化の研究の重要なポイントになると思います。
この論文はそのセンセーショナルな内容のためか、さまざまな場所で取り上げられたようです。
先週のNew Scientistの表紙を飾った記事、
Accidental origins: Where species come from -New Scientist
やNature Podcastのインタビュー、大学でのジャーナルクラブ(論文の輪読会のようなもの)のお題になったり、日本のブログでも取り上げている記事がありました。
赤の女王仮説 -サイエンスあれこれ
比較的良く知られているように、ダーウィンは著書『種の起源』の中で種分化の原因を必ずしも明確に説明していません。ダーウィンは自然選択によって適応的な進化がおこることを明確に示しました。しかし種分化については異なる適応の結果、異なるタイプの生き物のグループ、すなわち新しい種、が生まれるのは自明であるようにあつかっていたと記憶しています。(うろおぼえですが)
しかし、この論文の結果は自然選択は種分化の主原因ではない可能性を示しています。
論文内の印象的な部分を引用してみると、
"通常、種分化の後徐々におこる遺伝的な、もしくはその他の変化は、生殖隔離を引き起こしたイベントの原因であるよりは結果のようである"と、筆者らは述べています。
この考え方は、"種分化は適応的な変化によって徐々に引き起こされる"という従来の考え方に反しています。その点がメディアなどで取り上げられた理由だと思います。
しかしこの結果には納得のいく部分が多くあります。
まず自然のなかで実際に観察される種分化の痕跡は、ほとんどが稀なイベントの結果と考えられているからです。たとえば、地理的な隔離や離島への稀な移住のイベント、染色体数の変化などはすべてこれらに当てはまります。それに加えて生物の移動能力(稀なイベントの起こりやすさと考えられる)が種分化の頻度と関係があることも知られています。
ガラパゴス諸島のフィンチのように明らかに自然選択による適応の結果、種が分化したように見える例も存在します。しかし、このような明確な例はそれほど多くみつかっていません。(それを支持するとされる間接的な観察結果は多くあると思いますが。)
また、ショウジョウバエなどをつかった種分化と自然選択に関する研究も、選択を受けるハエのグループ間はすでに隔離されていることが前提になっています。
自然界において"自然選択の結果徐々におこる種分化"があまり観察されないのは、そもそもそれがあまり起こっていないからかもしれないというのは筋が通った考えだと思います。
しかし同時に種分化のプロセスが完全にランダム性のみに支配されているというのも、少し居心地の悪い気がします。
上のNew Sceintistの記事の中のDaniel Raboskyの指摘は的を得ていると思います。
"隔離の原因になることと分化の原因になることの2つが必要である"もし隔離のイベントが起こったとしても、完全な分化は自然選択無しでは起こりえないかもしれません。Pagelのいう"稀なイベント"がどれだけ稀であるかは、自然選択の存在によって決定されるのかもしれません。
いずれにせよ、筆者らがいう"稀なイベントのカタログのサイズを知ること"は種分化の研究の重要なポイントになると思います。
2010年3月14日日曜日
種分化の原動力-1
Phylogenies reveal new interpretation of speciation and the Red Queen
Venditti et al. 2009 Nature
種分化の原動力は自然選択ではなく稀なイベントであることを主張する論文。
この論文を最初に読んだのは12月でした。そのときは、内容やその解釈が難しかったのと、"種分化は稀なイベントによって起こる"という結論に対しても「なるほど、そうかも」ぐらいしか感じなかったので、きちんと読んでいませんでした。
ところが、この論文はメディア等に何度か取り上げられて話題になっているようです。マクロな進化の研究論文がメディアに登場することがあまりないのと、改めて読んでみるとかなり議論の的になりそうなことが書いてあったので紹介します。
長くなりそうなので、このエントリでは論文の内容の紹介のみをしたいと思います。
筆者らは、101の生物のグループから得られた系統樹の枝の長さのデータを使って、系統樹上における種分化の待ち時間(すなわち系統樹の内側の枝の長さ)の分布がどのような種分化のモデルによって最も良く説明されるのかを調べました。
比較に使われた分布は、(1)正規分布、(2)対数正規分布、(3)指数分布、(4)複数の指数分布の組み合わせ、(5)ワイブル分布の5つで、それぞれが異なる種分化のモデルから予測される枝の長さの分布をあらわします。
(1)は微小な種分化の要因が加算的に積み重なったときに種分化が起こるモデル。(2)は要因が積算的に積み重なったとき。(3)は一定の確率でおこる稀なイベントがそのまま種分化につながるとき。(4)は(3)が生物の系統ごとに異なる確率で起こるモデル。(5)は種分化の確率が時間によって変化するモデルをあらわしているそうです。
これらの分布のどれが系統樹の枝の長さの分布のデータとマッチするかを、筆者らは2つの方法で調べました。そして、そのどちらの結果においても指数分布(3)がもっとも良く観測された分布とマッチしたことを報告しています。
具体的には78%の系統樹は(3)と一致し、その後にワイブル分布、対数正規分布、(4)が8%、8%、6%と続き、正規分布と一致したデータはありませんでした。この傾向はすべての生物のグループにおいて共通でした。
この結果から筆者らは、多くの種分化はある1つの重要な稀なイベントの弾みによって起こっており、小さな原因が積み重なって起こる(すなわち自然選択によって徐々におこる)のではないと考えられると述べています。
また、この指数分布を生じるモデルの元では種分化は一定の確率でおこります。これはタイトルにある"赤の女王仮説"の予測する結果と同じです。しかし稀なイベントによって種分化が生ずるというモデルは、生物は常に競争に勝つために進化し続けるという赤の女王モデルとは一致しません。
そこで筆者らは赤の女王仮説の解釈の見直しを主張し、以下のように述べています。
この他にも種分化の確率が系統ごとに変化するモデル(4)と一致する系統樹がほとんど存在しなかったことから、従来知られている種分化のスピードが急速に変化するイベント(適応放散など)は進化の歴史において一般的ではないと述べています。
最後には種分化の研究において着目するべきなのは、ある生物のグループにどのような"稀なイベント"がおこりうるかをリストアップすることが、特定の適応のプロセスに着目するよりも重要であると、将来の研究の方向性を示しています。
なるほど、これはちょっとした話題になりそうな論文です。
この結果の解釈とメディアでの紹介については次のエントリで書こうと思います。
以下技術的なメモ
-形がとても似た5つの分布間のモデル選択を十分に正確に行えるのか
-枝の長さを通常の時間ではなく、分子進化の速さで計った部分がクール
-筆者らのモデルとは異なる仮定に基づく、"赤の女王"モデルがなぜ同様に種分化一定の系統樹を生じるのか
1つ目は2つの手法を比較してその結果がともに同じ結果を示していたので、信頼できるとは思いますが、どうしても疑いの目で見てしまいます。
2つ目は種分化の時間を推定することによるバイアスよりも、分子進化の速度のバラツキのほうが統計的に扱いやすいからでしょうか。
3つ目はオリジナルの"赤の女王"論文にあたってみるしかないみたいです。
Venditti et al. 2009 Nature
種分化の原動力は自然選択ではなく稀なイベントであることを主張する論文。
この論文を最初に読んだのは12月でした。そのときは、内容やその解釈が難しかったのと、"種分化は稀なイベントによって起こる"という結論に対しても「なるほど、そうかも」ぐらいしか感じなかったので、きちんと読んでいませんでした。
ところが、この論文はメディア等に何度か取り上げられて話題になっているようです。マクロな進化の研究論文がメディアに登場することがあまりないのと、改めて読んでみるとかなり議論の的になりそうなことが書いてあったので紹介します。
長くなりそうなので、このエントリでは論文の内容の紹介のみをしたいと思います。
筆者らは、101の生物のグループから得られた系統樹の枝の長さのデータを使って、系統樹上における種分化の待ち時間(すなわち系統樹の内側の枝の長さ)の分布がどのような種分化のモデルによって最も良く説明されるのかを調べました。
比較に使われた分布は、(1)正規分布、(2)対数正規分布、(3)指数分布、(4)複数の指数分布の組み合わせ、(5)ワイブル分布の5つで、それぞれが異なる種分化のモデルから予測される枝の長さの分布をあらわします。
(1)は微小な種分化の要因が加算的に積み重なったときに種分化が起こるモデル。(2)は要因が積算的に積み重なったとき。(3)は一定の確率でおこる稀なイベントがそのまま種分化につながるとき。(4)は(3)が生物の系統ごとに異なる確率で起こるモデル。(5)は種分化の確率が時間によって変化するモデルをあらわしているそうです。
これらの分布のどれが系統樹の枝の長さの分布のデータとマッチするかを、筆者らは2つの方法で調べました。そして、そのどちらの結果においても指数分布(3)がもっとも良く観測された分布とマッチしたことを報告しています。
具体的には78%の系統樹は(3)と一致し、その後にワイブル分布、対数正規分布、(4)が8%、8%、6%と続き、正規分布と一致したデータはありませんでした。この傾向はすべての生物のグループにおいて共通でした。
この結果から筆者らは、多くの種分化はある1つの重要な稀なイベントの弾みによって起こっており、小さな原因が積み重なって起こる(すなわち自然選択によって徐々におこる)のではないと考えられると述べています。
また、この指数分布を生じるモデルの元では種分化は一定の確率でおこります。これはタイトルにある"赤の女王仮説"の予測する結果と同じです。しかし稀なイベントによって種分化が生ずるというモデルは、生物は常に競争に勝つために進化し続けるという赤の女王モデルとは一致しません。
そこで筆者らは赤の女王仮説の解釈の見直しを主張し、以下のように述べています。
"種は常に同じ場所で走り続けているというよりも次の種分化の原因を待っている"また、
"種分化は自然選択の漸進的な力から自由であり、かならずしも他種や環境との『軍拡競争』を必要としない"とも彼らの考えを表現しています。
この他にも種分化の確率が系統ごとに変化するモデル(4)と一致する系統樹がほとんど存在しなかったことから、従来知られている種分化のスピードが急速に変化するイベント(適応放散など)は進化の歴史において一般的ではないと述べています。
最後には種分化の研究において着目するべきなのは、ある生物のグループにどのような"稀なイベント"がおこりうるかをリストアップすることが、特定の適応のプロセスに着目するよりも重要であると、将来の研究の方向性を示しています。
なるほど、これはちょっとした話題になりそうな論文です。
この結果の解釈とメディアでの紹介については次のエントリで書こうと思います。
以下技術的なメモ
-形がとても似た5つの分布間のモデル選択を十分に正確に行えるのか
-枝の長さを通常の時間ではなく、分子進化の速さで計った部分がクール
-筆者らのモデルとは異なる仮定に基づく、"赤の女王"モデルがなぜ同様に種分化一定の系統樹を生じるのか
1つ目は2つの手法を比較してその結果がともに同じ結果を示していたので、信頼できるとは思いますが、どうしても疑いの目で見てしまいます。
2つ目は種分化の時間を推定することによるバイアスよりも、分子進化の速度のバラツキのほうが統計的に扱いやすいからでしょうか。
3つ目はオリジナルの"赤の女王"論文にあたってみるしかないみたいです。
2010年3月11日木曜日
[論文]ソローの森と絶滅のリスク
Phylogenetic patterns of species loss in Thoreau's woods are driven by climate change
Willis et al. 2008 PNAS
気候変動による絶滅のリスクは系統樹上の特定のグループに偏っており、同じく偏りがある気候変動に対応する能力との間に相関関係があることを示した論文。
『森の生活』で有名なナチュラリスト、ヘンリー・D・ソローはアメリカ、マサチューセッツ州のコンコードの森で何年にもわたって植物の分布や花の開花次期を調べ、その記録を後世に残したそうです。そのコンコードの森は現在大部分が保護区に指定され、現在も植物の分布の調査が行われています。驚くべきことに森の60%が保護されているにも関わらず、27%の植物種がソローの時代から150年の間に失われたとされています。
そこには地域レベルの環境破壊の影響だけでなく、グローバルな気候変動の影響があると考えられます。
気候変動の影響は特定のグループの植物により大きく現れることが知られています。このような進化上近縁にある種がランダムが予測するよりも似通った特徴をもつことを、系統上での保存性(正しい日本語訳は知りません、phylogenetic conservertism)といいます。
この研究では特定のグループ内の種に共有される(すなわち系統上で保存される)特徴が、絶滅のリスクといかに関係しているかを調べています。
150年前、100年前、現代に行われた大規模な植物相の調査の結果と調査でみつかった植物の系統関係から、筆者らは、植物の開花次期の変化、開花次期の気温に対する反応とアバンダンス(生物の存在量のようなもの)の変化はともに系統樹上で保存されていること、そしてそれらに相関関係があることを示しました。
具体的には、顕著に個体数が減少したのはキクやランといった特定のグループに含まれる種でした。また開花次期が150年間で変化していない植物は個体数が減少し、冬の気温にあわせて開花次期を変化させる能力がある植物の個体数はあまり減少していませんでした。
この結果から、気候変動の生態系への影響を予測するとき、生物種の気候変動に対して反応する能力を考慮する必要があると筆者らは主張しています。
また系統上保存される特徴と絶滅のリスクの関係は、過去に起こった大量絶滅のパターン、特定のグループが大量に絶滅する、を説明する可能性があるとも述べています。
--
面白い論文だと思います。
有名なナチュラリストであるソローが調査したフィールドを対象にしたこと。気候変動の影響というタイムリーなトピックであること。そして、気候変動の影響を受けると思われる特徴(開花次期)を上手く選んで、それがグループごとに偏っておこる個体数の減少を説明することを示したこと。
まず、ソローの時代と比較して4分の1もの種が森から姿を消している事実に驚きました。このことは自然保護区などによる環境保護の限界を示しているのかなと思います。
そして、系統上のグループで共有される特徴が、非ランダムな絶滅のリスクを説明するというアイデアは、筆者が述べているように、他の生物にも広く適用できそうです。
いくつか気になった手法上の点をメモしておくと、
-不完全な系統樹を使って変数間の相関関係を調べていること
-アバンダンスの変化という進化しないと思われる特徴のconservatismを調べていること
このあたりの妥当性はちょっとよくわからないので、次の勉強の課題です。進化しない特徴でも、系統樹上での偏りは調べられそうな感じはしますが。
Willis et al. 2008 PNAS
気候変動による絶滅のリスクは系統樹上の特定のグループに偏っており、同じく偏りがある気候変動に対応する能力との間に相関関係があることを示した論文。
『森の生活』で有名なナチュラリスト、ヘンリー・D・ソローはアメリカ、マサチューセッツ州のコンコードの森で何年にもわたって植物の分布や花の開花次期を調べ、その記録を後世に残したそうです。そのコンコードの森は現在大部分が保護区に指定され、現在も植物の分布の調査が行われています。驚くべきことに森の60%が保護されているにも関わらず、27%の植物種がソローの時代から150年の間に失われたとされています。
そこには地域レベルの環境破壊の影響だけでなく、グローバルな気候変動の影響があると考えられます。
気候変動の影響は特定のグループの植物により大きく現れることが知られています。このような進化上近縁にある種がランダムが予測するよりも似通った特徴をもつことを、系統上での保存性(正しい日本語訳は知りません、phylogenetic conservertism)といいます。
この研究では特定のグループ内の種に共有される(すなわち系統上で保存される)特徴が、絶滅のリスクといかに関係しているかを調べています。
150年前、100年前、現代に行われた大規模な植物相の調査の結果と調査でみつかった植物の系統関係から、筆者らは、植物の開花次期の変化、開花次期の気温に対する反応とアバンダンス(生物の存在量のようなもの)の変化はともに系統樹上で保存されていること、そしてそれらに相関関係があることを示しました。
具体的には、顕著に個体数が減少したのはキクやランといった特定のグループに含まれる種でした。また開花次期が150年間で変化していない植物は個体数が減少し、冬の気温にあわせて開花次期を変化させる能力がある植物の個体数はあまり減少していませんでした。
この結果から、気候変動の生態系への影響を予測するとき、生物種の気候変動に対して反応する能力を考慮する必要があると筆者らは主張しています。
また系統上保存される特徴と絶滅のリスクの関係は、過去に起こった大量絶滅のパターン、特定のグループが大量に絶滅する、を説明する可能性があるとも述べています。
--
面白い論文だと思います。
有名なナチュラリストであるソローが調査したフィールドを対象にしたこと。気候変動の影響というタイムリーなトピックであること。そして、気候変動の影響を受けると思われる特徴(開花次期)を上手く選んで、それがグループごとに偏っておこる個体数の減少を説明することを示したこと。
まず、ソローの時代と比較して4分の1もの種が森から姿を消している事実に驚きました。このことは自然保護区などによる環境保護の限界を示しているのかなと思います。
そして、系統上のグループで共有される特徴が、非ランダムな絶滅のリスクを説明するというアイデアは、筆者が述べているように、他の生物にも広く適用できそうです。
いくつか気になった手法上の点をメモしておくと、
-不完全な系統樹を使って変数間の相関関係を調べていること
-アバンダンスの変化という進化しないと思われる特徴のconservatismを調べていること
このあたりの妥当性はちょっとよくわからないので、次の勉強の課題です。進化しない特徴でも、系統樹上での偏りは調べられそうな感じはしますが。
2010年3月8日月曜日
[論文]グッピーの進化と生態系への影響
Local adaptation in Trinidadian guppies alters ecosystem processes
Bassar et al. 2010 PNAS
生態系のプロセスに、短期間で起こった進化がどのような影響を与えるかを実験で確かめた論文。
筆者らは、異なる環境で異なる表現形を進化させているグッピーを使って、進化がどのように生態系のプロセスに影響を与えるかを確かめる実験を行いました。
具体的には、2種類の環境(ここでは肉食魚による捕食圧の違い、HP: high predation, LP:low predation)から持ってきた、異なるタイプのグッピーを同じ環境のメソコスム(自然を再現した大きな水槽のようなもの)に入れて4週間飼育し、藻類や無脊椎動物の存在量や窒素やリンの存在量といった生態系のプロセスを示す量を比較しました。
その結果、高い捕食圧の下(HP)で進化したグッピーを入れたメソコスムでは低捕食圧(LP)のものと比べて藻類による生産性は多く、落葉の分解のスピードや無脊椎動物の存在量は少なくなることが観測されました。
これらの違いは、HPとLPのグッピー間の個体群の密度の違いによって生じた採餌行動やNH4の分泌量の違いが連鎖的に生態系に影響を与えた結果であろうと筆者らは述べています。また実際のHPグッピーが生息する環境では高い藻類の生産性が観られ、捕食者とグッピーの相互作用が生態系の生産性に影響を与えている可能性を指摘しています。
--
はじめにこの論文のタイトルを見たとき、実際の進化をメソコスム内で起こしてその影響を調べる実験を行ったのか思ってちょっとドキドキしましが、実際には既に進化したとわかっている2種類の表現形を使ってその影響を調べたものでした。
直接進化を起こしたわけではなくても、その結果はとてもにおもしろいと思いました。
特に、結論で筆者も述べているように、生態学ではある種の個体は基本的に生態系内で同じ役割を果たすことが暗黙の内に仮定されていました。しかし、それが非現実ではないかとも言われてきました。この実験では、実際に異なる環境下で進化したグッピーの個体群は、生態系での役割も変化させることを示しています。
この結果は今まで静的に捉えられていた食物網や物質の流れは進化によって動的に変化すると言い換えるられるかもしれません。
進化生物学と生態学を統合する研究はこの研究に限らず最近の流行のようです。
Bassar et al. 2010 PNAS
生態系のプロセスに、短期間で起こった進化がどのような影響を与えるかを実験で確かめた論文。
筆者らは、異なる環境で異なる表現形を進化させているグッピーを使って、進化がどのように生態系のプロセスに影響を与えるかを確かめる実験を行いました。
具体的には、2種類の環境(ここでは肉食魚による捕食圧の違い、HP: high predation, LP:low predation)から持ってきた、異なるタイプのグッピーを同じ環境のメソコスム(自然を再現した大きな水槽のようなもの)に入れて4週間飼育し、藻類や無脊椎動物の存在量や窒素やリンの存在量といった生態系のプロセスを示す量を比較しました。
その結果、高い捕食圧の下(HP)で進化したグッピーを入れたメソコスムでは低捕食圧(LP)のものと比べて藻類による生産性は多く、落葉の分解のスピードや無脊椎動物の存在量は少なくなることが観測されました。
これらの違いは、HPとLPのグッピー間の個体群の密度の違いによって生じた採餌行動やNH4の分泌量の違いが連鎖的に生態系に影響を与えた結果であろうと筆者らは述べています。また実際のHPグッピーが生息する環境では高い藻類の生産性が観られ、捕食者とグッピーの相互作用が生態系の生産性に影響を与えている可能性を指摘しています。
--
はじめにこの論文のタイトルを見たとき、実際の進化をメソコスム内で起こしてその影響を調べる実験を行ったのか思ってちょっとドキドキしましが、実際には既に進化したとわかっている2種類の表現形を使ってその影響を調べたものでした。
直接進化を起こしたわけではなくても、その結果はとてもにおもしろいと思いました。
特に、結論で筆者も述べているように、生態学ではある種の個体は基本的に生態系内で同じ役割を果たすことが暗黙の内に仮定されていました。しかし、それが非現実ではないかとも言われてきました。この実験では、実際に異なる環境下で進化したグッピーの個体群は、生態系での役割も変化させることを示しています。
この結果は今まで静的に捉えられていた食物網や物質の流れは進化によって動的に変化すると言い換えるられるかもしれません。
進化生物学と生態学を統合する研究はこの研究に限らず最近の流行のようです。
2010年3月6日土曜日
[論文]進化生物学者への呼びかけ
Evolutionary Biology in Biodiversity Science, Conservation, and Policy: a Call to Action
Hendry et al. 2010 Evolution
進化生物学者は問題解決のためにもっと社会と関わっていくべきである、という意見を表明した論文。
共著者の数は18人。名の知れた進化生物学者の名前が見られます。
今まで進化生物学者は、生態学者などに比べて、自分たちの知識を社会の役に立てるための積極的な活動をあまりしてこなかった。しかし、現在の生物多様性の損失などの問題に対応するには進化生物学の知識は社会にとって不可欠である。そこで進化生物学者はそれらの問題解決のためにより積極的に知識を提供していこう、というのが全体の内容です。
進化生物学者が関わっていくべき分野は、以下が挙げられていてます(3と4は実際には一体になっている)。
1) 多様性の記述。分類学や系統学は多様性を記述する学問であり、生物多様性の理解の基礎になる。現代ではより簡単に誰でもアクセスできるデータベースの構築も含まれる。
2) 多様性の起源を理解する。現在の生態系は進化的時間の中で形作られており、その起源となるプロセスを理解することが、保全の優先順位の決定や人間活動の与える影響を予測する基礎になる。
3&4) 人間活動によって起こる進化とそれが生態系にあたえる影響の理解。人間活動が従来考えられていたよりもずっと速い生物の進化を引き起こすことが近年知られてきた。また速いスピードで起こる進化が生態系に与える影響の研究も行われている。その2つをあわせ、生物の人間活動への進化的反応と、そこから生じる生態系への影響を理解することが、生態系の保全をはかる上で欠かせない。
以上の4つのことで進化生物学者は社会に貢献できるとのこと。
--
進化生物学がなんの役に立つのか、と聞かれたら、僕はは少し答えに窮してしまいます。役に立たないけど興味深いです、と答えるかもしれません。(もちろん役に立つ進化の研究をしている研究者は多くいますが)
この論文はそんな進化生物学者が社会に貢献できる分野を、流行の生物多様性の問題とからめて、上手く整理して挙げていると思います。自分自身やや同僚がやっている研究も上の4つの領域の少なくともどれか1つには当てはまるように見えます。
進化生物学は生物の多様性の起源を探る学問である、と聞いたことがあります。そのことと生物多様性の重要さを考えあわせると、役に立たないというほうが本当はおかしいのかもしれません。(もしかしたら"生物多様性"という概念自体、生態学者や進化生物学者が役立たずであるという考えを払拭するために作られたのかもしれませんが)
Hendry et al. 2010 Evolution
進化生物学者は問題解決のためにもっと社会と関わっていくべきである、という意見を表明した論文。
共著者の数は18人。名の知れた進化生物学者の名前が見られます。
今まで進化生物学者は、生態学者などに比べて、自分たちの知識を社会の役に立てるための積極的な活動をあまりしてこなかった。しかし、現在の生物多様性の損失などの問題に対応するには進化生物学の知識は社会にとって不可欠である。そこで進化生物学者はそれらの問題解決のためにより積極的に知識を提供していこう、というのが全体の内容です。
進化生物学者が関わっていくべき分野は、以下が挙げられていてます(3と4は実際には一体になっている)。
1) 多様性の記述。分類学や系統学は多様性を記述する学問であり、生物多様性の理解の基礎になる。現代ではより簡単に誰でもアクセスできるデータベースの構築も含まれる。
2) 多様性の起源を理解する。現在の生態系は進化的時間の中で形作られており、その起源となるプロセスを理解することが、保全の優先順位の決定や人間活動の与える影響を予測する基礎になる。
3&4) 人間活動によって起こる進化とそれが生態系にあたえる影響の理解。人間活動が従来考えられていたよりもずっと速い生物の進化を引き起こすことが近年知られてきた。また速いスピードで起こる進化が生態系に与える影響の研究も行われている。その2つをあわせ、生物の人間活動への進化的反応と、そこから生じる生態系への影響を理解することが、生態系の保全をはかる上で欠かせない。
以上の4つのことで進化生物学者は社会に貢献できるとのこと。
--
進化生物学がなんの役に立つのか、と聞かれたら、僕はは少し答えに窮してしまいます。役に立たないけど興味深いです、と答えるかもしれません。(もちろん役に立つ進化の研究をしている研究者は多くいますが)
この論文はそんな進化生物学者が社会に貢献できる分野を、流行の生物多様性の問題とからめて、上手く整理して挙げていると思います。自分自身やや同僚がやっている研究も上の4つの領域の少なくともどれか1つには当てはまるように見えます。
進化生物学は生物の多様性の起源を探る学問である、と聞いたことがあります。そのことと生物多様性の重要さを考えあわせると、役に立たないというほうが本当はおかしいのかもしれません。(もしかしたら"生物多様性"という概念自体、生態学者や進化生物学者が役立たずであるという考えを払拭するために作られたのかもしれませんが)
はじめに
読んだり考えたたりしたことをどこかに保存しておく必要がでてきたので、ここに書いていくことにします。
内容は学術論文、本、ウェブなどを読んだ感想です。
博士課程の学生、専攻は進化生物学なので、その方面の内容が多くなると思います。
内容は学術論文、本、ウェブなどを読んだ感想です。
博士課程の学生、専攻は進化生物学なので、その方面の内容が多くなると思います。
登録:
コメント (Atom)